大きな塔と小さなお社
· パーマリンク
むかしむかしあるところに、とても大きな塔がありました。近くの街の長老も一体いつからあるのかわからないほど昔からある、見上げれば首が痛くなるような高さの塔でした。
いつの頃からか、その塔のてっぺんに登れば世界のすべてを知ることができるとまことしやかに語られはじめ、多くの人たちがてっぺんを目指して塔を登っていきましたが誰も登れませんでした。
塔に入って階段を登ろうとすると、いつの間にか元いた場所に戻ってしまうのです。何人も何人も試してみましたが、やっぱり戻ってしまいます。
ある人たちは塔の外側から登ろうとしましたがだめでした。ある人たちは塔の階段を使わずに登ろうとしましたが、やっぱりだめでした。誰も彼も登れなかったので、次第に塔に登ろうとする人たちは減っていきました
大きな塔に登る人たちがだんだんといなくなり、一年たち、十年たち、数十年たち、塔も蔦で覆われて、大きな塔は本当に誰からも忘れられてしまいました。
そんなある日、もうすぐ日も暮れようかという頃合い、遠くから一人の青年が歩いてきました。青年は、街から街、村から村、山から海、東から西、南から北へと渡り歩く行商人でした。
青年は塔に着くなり大きなため息をつきました。日暮れまでに次の村まで辿り着けそうになかったので、なんとか一晩休める場所をと急いで歩いてきたのに、そこにあったのはなんとも不気味な塔だったのです。
青年は一人つぶやきました。こんな不気味な場所で夜を明かすなんてそんな怖いことはない、いまからでも別の場所を探そうか。青年は一人つぶやきました。もうすぐ日も暮れる、今日はここで我慢しよう。
青年は大きな塔の周りを歩きはじめました。どこか風が防げるような場所を探していたのです。塔の中も少し見てみましたが、薄暗く、とても安心して眠れそうにありません。
しばらく塔の周りを歩いていましたが、ふと小さな社があることに気が付きました。それは本当に小さなお社で、こんな大きな塔のそばにあるには少しばかり不釣り合いな、そんなお社でした。
青年はお社に手を合わせて、お祈りをしました。自分は行商をなりわいとしていること、今日は偶然ここで夜を過ごすことになったこと、心細いのでぜひ見守ってほしいこと、そんなことをお願いしたのです。最後に晩御飯のなかからほんの少しのお供え物をして、今日はここで寝ることに決めました。
少し無理をしたせいでしょうか、青年はすぐに深い眠りに落ちました。
気がつくと青年はとても高い場所にいました。そこからは地平線が丸く見えるほど、とても遠くまで見ることができました。あっちの方には山が見え、あっちの方には海が見え、街や村、それらをつなぐ道など色んなものが見えました。
青年は、なんてきれいなんだろう、僕はどっちからきたんだろう、次はどこへ行くんだろう、思わずそうつぶやきました。ふと気がつくと、すぐそばに女の人が立っています。青年はびっくりして、今のつぶやきを聞かれていなかっただろうかと少し恥ずかしい気持ちになりました。
あなたの知りたいことはなんですか、女の人は青年にそう尋ねました。青年はびっくりしました。びっくりしていると女の人はもう一度、あなたの知りたいことはなんですか、と尋ねました。
知りたいことはいくらでもありました。どこに街に行けば安く品物を仕入れられるだろう、どこの街に行けば高く売れるだろう。あの村では何が必要なんだろう、今年の秋に収穫の多い村はどこだろう、どこになに持っていけば売れるだろう。そんなことが頭の中でぐるぐると回っていました。
そんなときでした。ふと青年が顔を上げると、つい数日前こ行商で訪れた村が目に入りました。隣町に住む孫娘からあずかった荷物を届けたおじいさんは元気かな、すごく喜んでいたな。子供が生まれたからと気前よく買ってくれたあの夫婦は元気かな。一晩泊めてもらい面白い話を聞かせてくれたおばあさん。
そういえばおばあさんからは次に行く街に住む息子さん夫婦に届け物をしてほしいと頼まれていたな。なんでも冬の間にこしらえた織物で、お嫁さんは裁縫がとても上手でと色々聞かされたな。いつの間にか青年の頭の中にはそんなことがとめどなく思い出されました。
ふと我に返ると、女の人が少し困ったような顔でこちらを見ていることに気が付きました。恥ずかしくなった青年は、少しだけ俯いたあと、知りたいことはいっぱいあります、でも、それを聞いて済ましてしまうのはすごくもったいないと思うのです。だから僕は次の街に行こうと思います。荷物を待ってくれている人がいるんです。と答えました。
意識が遠くなる中、女の人が少し困ったような、少し嬉しそうな顔をしていたような、そんな気がしました。
朝、青年は目を覚ますと身支度を整え、お社に向かってお祈りをしました。荷物を準備し、預かった織物を確認すると、もう一度だけお社にお祈りをして、青年は次の街へ旅立っていきました。
あとには大きな塔と小さなお社が朝日を浴びて輝いていました。
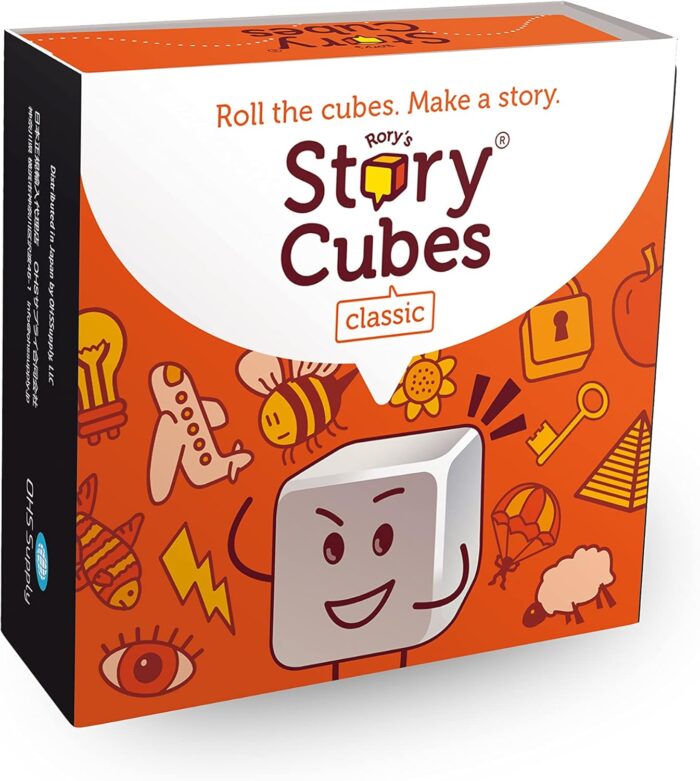
ローリーズ・ストーリー・キューブス
Rory’s Story Cubes (ローリーズストーリーキューブス) に日本仕様のパッケージが登場!即興でストーリーを創作して楽しむ、ポケットサイズのお話サイコロです。9つの絵をつなげて1つのお話をつくれるかな?このゲームでは競ったり勝敗を決めたりすることはありません。お一人でもたくさんでも、子どもも大人もお楽しみ頂けます。